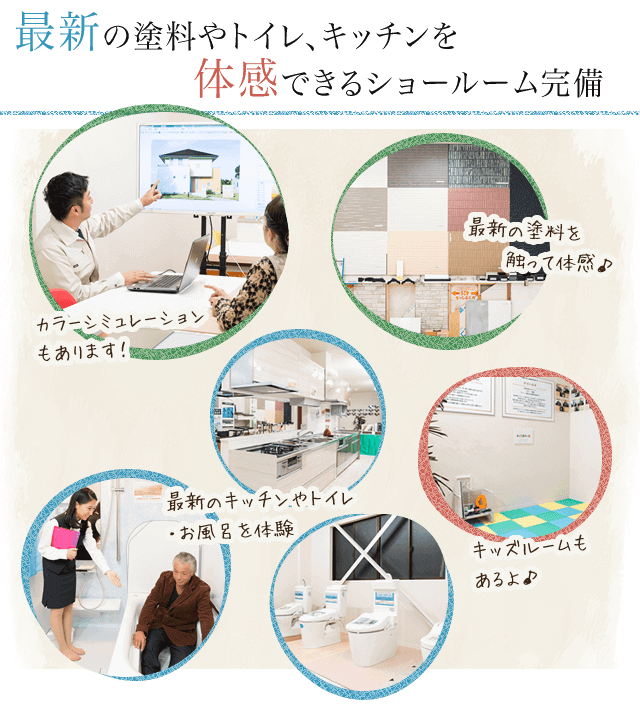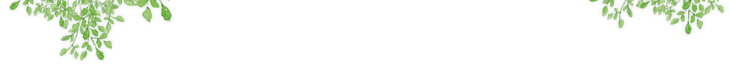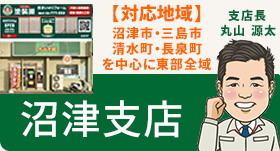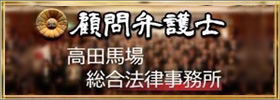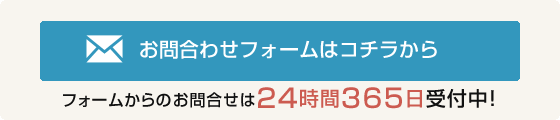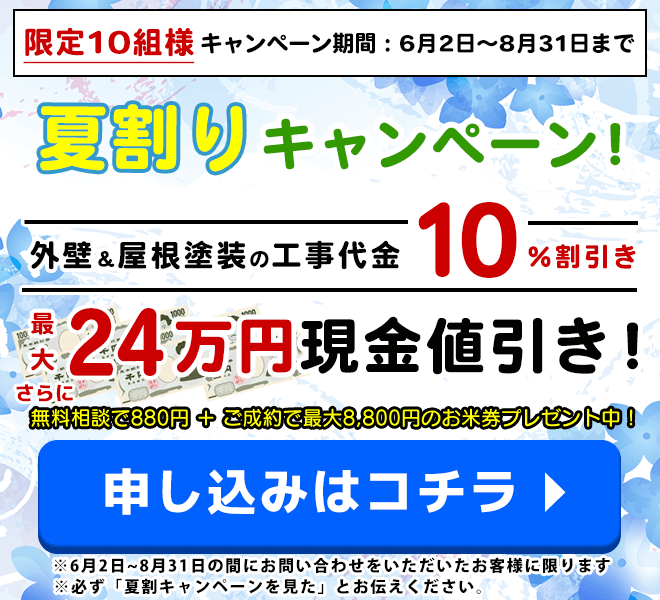お風呂のカビを取る方法や防止するには?
毎日使うお風呂場で発生するカビ。掃除もこまめにしているのになぜカビが発生するのか?そもそもカビはどこからやってきて、どうやって繁殖しているのでしょうか?
ここでは、簡単にできるカビ対策や除去の方法を説明していきます。
カビはどこからやってくる?
カビの胞子というのは、目には見えないですが、実は空気中の含まれています。その胞子が風に乗り、新しい場所で水分や栄養分を取り込み成長し、発芽をします。そして、成長したカビが新しいカビ胞子を空気中に飛ばし、繁殖をします。
つまり、カビの”元”が空気中にたくさん漂っている為、原因そのものを絶つのはかなり難しいです。しかし、カビが成長する為にはいくつかの条件があります。その条件をクリアしない様にすれば、カビの発生をかなり抑える事ができます。
カビが発生する3つ(栄養・温度・湿度)の条件
■ 条件1:栄養
カビの栄養というのが、汚れや埃の中にタンパク質です。タンパク質はお風呂場の中でいえば、アカや石鹸カスなどに含まれています。
■ 条件2:温度
湿度が高いだけでなく、温度も高いとカビが発生しやすくなります。20~30度くらいがカビの好む温度です。春~夏にかけてのちょうど暖かくなる温度になり、人間にとって過ごしやすい温度ですが、カビにとっても同じことになります。
■ 条件3:湿度
「湿度が高くじめじめした所ではカビが生えやすい」と言われる様に湿度80%以上だと、非常にカビが生えやすくなります。雨が降った日や、洗濯物を部屋干ししていたりするとこのくらいの湿度になってしまいます。
お風呂場は湿度、温度、栄養の3つの条件が整っています。まさに、カビが繁殖するための環境といわんばかりです。
カビの発生を抑えるカンタン予防対策
カビが発生する3つの条件を揃えなければ、カビの発生を抑える事が出来ます。お風呂上がりにできる、お手軽なカビ予防をご紹介します。
■ その1:栄養対策
カビは浴槽に残った石鹸カスや、アカから栄養を取っています。これらをキレイに洗い流す事でカビの栄養補給を断つ事ができます。
また、洗い流す時に45度以上のお湯を使用する事で、カビの胞子を死滅させる事ができます。
■ その2:温度対策
暖かいお風呂に入るとどうしても浴室内の温度は高くなってしまいます。その浴室内の温度を下げる為に、壁や床を冷水で洗い流しましょう。これらを「その1:栄養対策」を行った後にやると、さらに効果がUPします。
■ その3:湿度対策
湿度対策には換気扇を回す事をお勧めします。ただし、2時間くらい回すだけでは、ほとんど効果がないため、できれば、一晩中まわしっぱなしにするのが、最も効果があります。窓がある場合は開けて、浴室内の湿度を下げるようにしましょう。
市販のカビ取り剤でのカビを取る方法
予防策をしていても、気づかないうちにカビが生えてしまった、などという事があります。その場合、市販のカビ取り剤を使っても落ちないなどと良くありませんか?
重曹や酢で環境に配慮したお掃除方法もあるのですが、見えない部分のカビは時間をかけてじっくり根を下ろしてしまっている場合が多く、残念ながら退治しにくいです。
ここでは、市販の塩素系のカビ取り剤を使用し、効果的にカビを取る方法をご紹介します。
■ ステップ1
通常の浴室用洗剤でお掃除をします。カビの上が汚れている状態だとカビ取り剤が密着しにくく、効果が十分に発揮できません。
■ ステップ2
お掃除後、浴室内をいったん乾燥させます。水分がたっぷりついている状態だと、カビ取り剤が薄まってしまったり、カビに密着しにくかったりします。乾くまで待つか、タオルでふき取るかはどちらでも大丈夫です。
■ ステップ3
乾燥したら、カビ取り剤を吹きかけます。山盛りかけるよりも、薄くまんべんなくかけます。カビ取り剤は空気と反応して、カビを取るので、山盛りだと空気と反応しにくく、効果が薄れてしまいます。
■ ステップ4
垂れやすい場所や、しっかり染み込ませたい場合はティッシュやキッチンペーパーを細くこより状にしたものに、カビ取り剤を染み込ませ、貼り付けましょう。
■ ステップ5
天井など目の高さより上の場所にはスプレーしないようにと、カビ取り剤の注意書きに書いてあると思います。天井のカビを取る為には、ティッシュやキッチンペーパーにカビ取り剤を染み込ませ、トントンと叩き付ける様にして下さい。
天井に「ステップ4」の方法で貼り付けると、落ちてくる場合が多いためです。カビ取り剤は少量でも空気と反応し、効果がある為トントンするだけで大丈夫です。取れなかった場合は、何度か繰り返してみてください。
■ ステップ6
こすらずに待ってください。早く、しっかりとと思いこすってしまいがちですが、ここは化学反応でカビを除去してくれるのを待ちます。ゴムパッキンや目地は、ゴシゴシこするとカビ菌が中に入り込んでしまうこともあるので、こするのは厳禁です。
■ ステップ7
最後によく流して終了です。